平成22年(行ケ)第10234号 審決取消請求事件 (知財高裁 平成23年3月23日判決)
平成25年6月19日 執筆/平成25年7月4日掲載
弁理士 井出佳一
1.事件の概要
当初明細書等に明示的に表現されていない数値範囲への訂正請求が認められたが、数値範囲に臨界的意義が存在しないため、進歩性の判断に誤りがあるとして無効審判に対する請求不成立の審決が取り消された事件。
2.事件の経緯
原告 吉野石膏株式会社
被告 株式会社名ナコード
被告 太平洋セメント株式会社
| 平成15年6月25日 | 特許出願 |
| 平成20年10月17日 | 特許権の設定登録 |
| 平成21年10月28日 | 特許無効審判の請求 |
| 平成22年1月22日 | 答弁書及び訂正請求書提出 |
| 平成22年4月22日 | 口頭審理(口頭審理陳述要領書提出) |
| 平成22年6月15日 | 審決 無効とすることはできない |
| 平成23年3月23日 | 判決(平成22年(行ケ)第10234号) 審決を取り消す |
3.技術背景
石膏ボード…石膏を主体とする板材を特殊な原紙で被覆したもの。建築用資材として使用されている。建築現場においては、使用部位の寸法に合わせて切断され、廃材が多量に発生する。廃材は、埋め立て処分されるため、処理コストが大きい。このため、廃材を加熱して原紙を灰化し、廃材から石膏を回収して再利用している。
4.請求の原因(無効審判)
<無効審判での経緯>
原告は、本件特許(特許第4202838号)の請求項1ないし5に対し、特許法29条2項に違反するとして特許無効審判を請求した。その後、被告は訂正請求を行った。特許庁は、被告の訂正請求を認め、本件審判の請求は成り立たない旨の審決(維持審決)をした。
<訂正前の特許請求の範囲(請求項1のみ記載)>
【請求項1】
内筒の内部で燃料を燃焼させて該内筒の下部の開口部から燃焼ガスを噴出させ、前記内筒を囲繞し、下部が逆円錐状に形成された本体に石膏廃材を供給し、該本体の内部で該石膏廃材を330℃以上840℃以下に加熱しながら、前記燃焼ガスによって流動化させ、生じた無水石膏を前記本体の内部から外部に排出することを特徴とする無水石膏の製造方法。
330℃…石膏廃材等の二水石膏からⅡ型無水石膏を焼成するために必要な温度。
840℃…混和剤として含有されるナフタレンスルホン酸基の分解温度(850℃)や、石膏自体の分解温度(1000℃)まで加熱されることを避けるための温度。
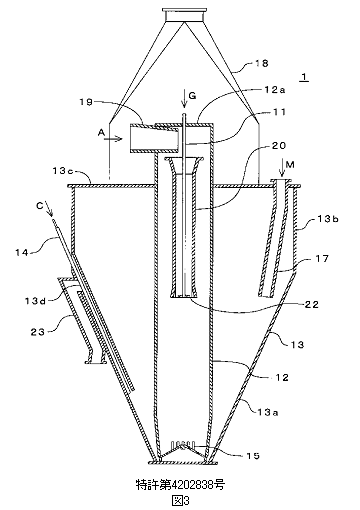
1…無水石膏焼成炉、11…燃料供給管、12…内筒、13…本体、13a…下部、15…スリット(開口部)17…飛散ダスト戻し管、19…燃焼用空気管。
<訂正後の特許請求の範囲>
【請求項1】
内筒の内部で燃料を燃焼させて該内筒の下部の開口部から燃焼ガスを噴出させ、前記内筒を囲繞し、下部が逆円錐状に形成された本体にナフタレンスルホン酸基を含む石膏廃材を供給し、該本体の内部で該石膏廃材を、該本体出口における粉粒体温度が330℃以上500℃以下になるように加熱しながら、前記燃焼ガスによって流動化させ、生じたⅡ型無水石膏を前記本体の内部から外部に排出することを特徴とする無水石膏の製造方法。
訂正前は本体の内部での温度で規定されていたのに対して、訂正後は本体出口での温度で規定されている。また、温度の上限値が、840℃から500℃に変更されている。
明細書などに、温度の上限を500℃とすることの明示的な記載はない。実施例には、炉出口粉粒体温度が460℃になることを目標とした旨の記載がある。また、実施例における炉出口粉粒体温度が、460℃(実施例1)、470℃(実施例2)、450℃(実施例3)、470℃(実施例4)であった旨の記載がある。
<請求人(原告)の提出した証拠>
粉粒体の温度が「350℃以上」になるように加熱しながら燃焼ガスによって流動化させる旨の記載がある文献(特公昭60-9852)、ナフタレンスルホン酸基の分解温度が850℃であるため、加熱温度の上限を「850℃」や「800℃」に設定する旨の記載がある文献(特開2002-086126、特開平10-230242)、その他、温度範囲として「300~800℃、好ましくは500~600℃」、「360~600℃」との記載がある文献など。
<特許庁の判断>
(1) 本体出口において測定される温度は、本体内部での加熱温度と実質的に変わらないとみることができる。(2) 上限値を500℃以下とすることに臨界的意義はないと認められる。(3) 当初明細書などに具体的に記載された460℃より多少高めの温度を上限として温度範囲を減縮することは新たな技術的事項を導入するものではない。したがって、訂正は適法であり、提出された証拠など及び周知事項に基づいて容易に発明することができたとはいえない。
5.争点
(1)訂正請求を認めたことが適法か。
(2)訂正後発明は進歩性を有するか。
<争点(1)について>
原告の主張
(1) 石膏廃材の加熱温度を本体内部で規定することと、炉本体出口の温度で規定することは、技術的な意義が異なる。よって、特許請求の範囲の実質的な変更である。
(2) 加熱温度の上限値を500℃にする訂正は、新規事項の追加である(特許請求の範囲を減縮する訂正には該当しない)。
被告の反論
(1) 当初明細書等に炉の本体内部の温度が製品排出部の温度と実質的に同じとする明文はないが、当初明細書等にも記載され、審決も述べるように、石膏廃材の粉粒体が本体内部で全体として略均一な温度となった後に直接外気にさらされることなく排出される本体出口における粉粒体の温度は、本体内部での加熱温度と実質的に変わらないとみることができるのであるから、明文がないことは審決の理由が誤っていることを理由付けるものではない。
(2) 訂正前の特許請求の範囲の記載である「330℃以上840℃以下」の温度範囲内には「500℃」という値の温度を含んでいることは明らかであり、当初明細書等の発明の詳細な説明にも目標温度460℃に対する実際の測定温度が450℃ないし470℃の範囲で変動していることが記載されている。そうすると、当初明細書等には、「500℃」という特定の数値が「明記」されていなくとも、「330℃以上840℃以下」という記載中に、「500℃」という値自体は実質的に記載(明示)されているのである。したがって、訂正事項は、当初明細書などの範囲内の記載である。
裁判所の判断
(1) 本体出口において測定される温度は、本体内部での加熱温度と実質的には変わらないとみることが可能であるから、新たな技術的事項を導入したものとはいえない。
(2) 「500℃」という値は当初明細書等に明示的に表現されているものではない。そこで、上記「500℃」という値が当初明細書等に記載された事項から自明であるといえるかどうかが問題となる。しかし、「500℃」という特定温度は、もともと訂正前の「330℃以上840℃以下」の温度の範囲内にある温度であるから、上記「500℃」という温度が当初明細書等に明示的に表現されていないとしても、硫黄酸化物の発生抑制のための温度として分解温度以下である以上他の温度と異なることはなく、実質的には記載されているに等しいと認められること、当初明細書等に記載された実施例においては、炉出口粉粒体温度が「460℃」になることを目標とした旨が記載され、当初明細書等の【表2】には、実施例における「炉出口粉粒体温度(℃)」が、「460℃」(実施例1)、「470℃」(実施例2)、「450℃」(実施例3)、「470℃」(実施例4)であったことが記載されていることからすれば、具体例の温度自体にも開示に幅があるといえる。したがって、具体的に開示された数値に対して30℃ないし50℃高い数値である近接した「500℃」という温度を上限値として設定することも十分に考えられること、また、訂正後の上限値である「500℃」に臨界的意義が存しないことは当事者間に争いがないのであるから、訂正前の上限値である「840℃」よりも低い「500℃」に訂正することは、それによって、新たな臨界的意義を持たせるものでないことはもちろん、500℃付近に設定することで新たな技術的意義を持たせるものでもないといえるから、「500℃」という上限値は当初明細書等に記載された事項から自明な事項であって、新たな技術的事項を導入するものではないというべきである。
したがって、特許庁が訂正請求を認めたことは適法である。
<争点(2)について>
原告の主張
訂正後の上限値である500℃に臨界的意義は存しないのであるから、上限値を500℃とすることにはなんらの創意工夫も存在しない。臨界的意義がないことは、上限温度が840℃であっても460℃であっても500℃であっても作用効果に顕著な差がないことを意味している。
被告の反論
上限温度を500℃にすることで、ナフタレンスルホン酸基の分解温度以上に加熱しないという技術的意義を有している。
裁判所の判断
上限値を「500℃以下」と設定した点については臨界的意義はもちろんのこと何らの技術的意義も存しないのであるから、「500℃」という特定の温度を設定することについては格別の創意工夫を要しないこと、さらに、証拠として提出された文献において、温度範囲を「400~850℃」、「300~800℃、好ましくは500~600℃」、「360~600℃」と設定していることからすれば、硫黄酸化物の発生を極力抑制することを念頭に置いて上限を「500℃以下」と設定することは、当業者が容易に想到し得ることであると認めるのが相当である。 この点に関して、被告らは、訂正後発明1において「本体出口における粉粒体温度が330℃以上500℃以下になるように加熱」することで、本体の内部で石膏廃材を330℃以上840℃以下に加熱することができるのであるから、「500℃」という上限温度は「ナフタレンスルホン酸基の分解温度(850℃以上)」以上に加熱しないという技術的意義を有しているとし、「500℃」という温度設定に技術的意義があることを前提として縷々主張するが、上記のとおり、「500℃」という温度設定には何らの技術的意義もないのであって、仮に被告らの主張を前提としても、「500℃」という温度と「850℃」というナフタレンスルホン酸基の分解温度を結びつける記載もないのであるから、「500℃」という温度設定に被告らの主張するような技術的意義を認めることはできない。したがって、「500℃」という温度設定に技術的意義があることを前提とする被告らの主張はいずれも採用することができない。 よって、訂正後発明1について容易想到ではないとした審決の判断は誤りである。
6.結論
訂正は適法であるが、進歩性の判断を誤った違法があるため、審決取消。
7.まとめ(実務上の指針)
明細書などに記載した数値範囲内であれば、明細書などに明示的に表現されていない数値であっても訂正が認められる場合がある。これは、訂正後の数値に臨界的意義が存在しないため、それによって新たな技術的意義を持たせるものではなく、新たな技術的事項を導入するものではないといえるからである。
しかしながら、訂正が認められることと、それによって無効理由が解消するかどうかは別問題である。臨界的意義を有さない数値に訂正したとしても、その数値が臨界的意義を有さないことを理由として進歩性が認められない可能性は高いと考えられる。このため、明細書などの訂正を行う際にはこれらに留意して訂正を行うべきである。